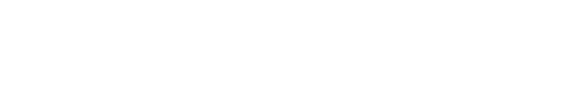ロベスピエール ~宝塚の成功~
今年の東京宝塚劇場は、
新生雪組の「ひかりふる路」と「SUPER VOYAGER」で幕を開けた。
「ひかりふる路」に高い関心があった私は
昨年11月に宝塚大劇場まで足を運び初見している。
「ひかりふる路」の主人公ロベスピエールは、
フランス革命時代を題材にした宝塚の作品においてはしばしば登場するが、
主役ではない。
主人公として描くとなると、「宝塚的」にはなかなか難しいと感じていた。
「自由・平等・博愛」を掲げたフランス革命の立役者でありながら、
革命達成後の彼の生涯は、華やかな宝塚の舞台には相応しくない。
彼は革命政権の維持のために、うち続くジロンド党やジャコバン内部の党派対立の中で、
革命の理念とはほど遠い恐怖政治の指導者として名を馳せ、
そして自らもまた、テルミドールの政変でその渦の中で生涯を閉じることになるのである。
さて、そんなロベスピエールを宝塚では、どのように描くのであろうか。
原作がある翻案ものは多くある。
しかし先に述べた生涯を送ったロベスピエールの歴史的史実から
宝塚の舞台に載せるのはどんなストーリーでどんな脚本なのか。
多くのファンを魅了しているフランス革命ものは「ベルばら」を筆頭に、
「スカーレットピンパーネル」も、「1789-バスティーユの恋人たち-」も、
「二都物語」も、有名な漫画か、著名な小説か、
欧米で成功したミュージカルの宝塚版である。
これに対し、光と影のあるロベスピエールを主人公に取り上げ、その一生を描くなら、
どうしても恐怖政治という影の部分を舞台にのせざるを得ない。
主人公のこの影を宝塚のファンに許容される形でどのように描くのか、
期待と不安が胸に抱き劇場への路を歩んだ。
さて、生田大和先生の脚本はお見事というしかない。
さすが「わが愛する宝塚」は、簡単に私の期待を裏切ることはなかった。
この作品の成功は、マリアンヌという創作上の女性を登場させたことに尽きる。
マリアンヌは、両親や婚約者を革命で殺害された貴族である。
革命の象徴的指導者ロベスピエール殺害のために革命家ロベスピエールに接近する。
何度かの機会がありながら、殺害に至らない。
失敗か、何らかの躊躇か、敵役に対する愛情の芽生えか。
自然な史実の流れに合わせて、マリアンヌはロベスピエールの持つ崇高な理念に、
ときに対峙し、ときにその理念に共鳴し、
しかし現実政治の中での理念に反する恐怖政治には凜として批判的な立場をとり、
最後にロベスピエールが挫折したときには、その理念の意義を説く。
ストーリーの流れを二人の関係性の変化で転換させながら
すべてが自然の流れの中に収まっている。
主人公の恐怖政治もそのまま舞台にのせながら宝塚的な許容の範囲に収まっている。
一方現実政治は、国王の処刑を巡る党派間の対立、
ジャコバンとジロンドの対立に留まらず、ジャコバン内部での争い。
生身の人間の感情を無視しての政治はありえないとのダントンとの確執、
そして自らもまたテルミドールの乱で、断頭台に向かうこととなる。
マリアンヌはすでにロベスピエールの指揮によって捕らえられ牢獄にある身。
テルミドールの乱でロベスピエールが捕らえられる。
自らの理念が無意味だったと語るロベスピエールに対し、
それは意義あることと励まそうとするマリアンヌ。
互いに愛情を感じながら現実政治の前に無力な理念と無力な愛。
そのやりとりは切なく胸を打つ。
「自由、平等、博愛」の思想は、
200年以上経過した今の世にあっても色あせることなく人類の普遍的価値である。
総じてこの作品は宝塚としても大成功であろう。
それは、この生田大和のストリート共に、望海風斗と真彩希帆の特筆すべき歌唱力、
そしてワイルドホーンによって提供された楽曲の素晴らしさあってこそであることは
言うまでもない。
私の青春
さて、話は変わるが、この観劇後は私の青春時代の体験と重なりあい、
なんとも言えぬ感慨に陥っている。
この舞台の歴史のように、どんな理想も、現実政治の中で翻弄されるならば、
その価値を否定する真反対の行動へと堕す危険がある。
すでに歴史的な事実に属する事柄のようではあるが、
1970年代の学生運動を生きた身には、それが二重写しとなって迫ってきる。
私は、弁護士になることを決意して法学部に入学するまでは、
医師なることを目指して医学部に在籍していた。
そこで私は学生運動に走るのであるが、
私の属した学生組織が一時期発行していた機関誌のタイトルが「若きジャコバン」というのも
何かの縁であろうか。
当時の学生運動が、全共闘運動として全国の大学に燎原の火の如くに展開され、
反戦運動と結びつき高揚したのち、機動隊による物理的鎮静化と、
会派の対立による消耗戦により大衆の支持を失って、
たどったのは分裂と孤立の道で有り、最後の極端な末路の例が、浅間山荘事件であった。
安田講堂の機動隊との攻防戦は今では歴史の一コマであるが、
私はその一週間前にその中で開催された医学連大会に参加していた。
その中にいた多くの学生のその後のすべては知るよしもないが、
当時医学連に結集していた東北地方の医学生の一人が浅間山荘近くで死を迎えたことは
一つの歴史的事実である。
かなり多くの同世代が共有したはずの体験とはいえ、
現在宝塚の舞台の中に、
このような感慨をもって観劇できることの運命の不思議さを感ぜずにはいられない。
そして、また修復された、その安田講堂で、
私は昨年、日本弁護士連合会主催の業務改革シンポジウムで主催者を代表し、
開会の挨拶を行う機会を得たことも、
さらにこの巡り合わせに、もう一本の強い糸が撚り合わさったという感慨が加わる。
過激派から歌劇派へ。
今の私自身の歴史を繋ぐ言葉である。
願わくは、宝塚を楽しむことができる平和な世が続くことを祈りたい。