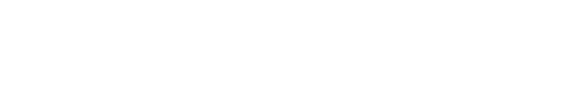明治の文豪の作品を題材に愛を描く
宝塚の試み、その忘れ得ぬ感動を再び
私が高校生のときに読んだ美文調の格調高い文章で綴られた森 外「舞姫」の記憶。それは美しい文章とは裏腹に、衝撃的な結末の記憶であった。
実際そこにはいない子供のためにおむつを取り出す動作を単調に繰り返す「若き狂女」。自ら信じた愛が壊れ
ていくとき、人間の精神もまた壊れていくという底知れない恐怖を感じた記憶は、「パラノイア」と「襁褓」というそ
のとき初めて知った二つ単語と共に私の脳裏に焼き付いていた。
舞姫の主人公の愛の苦悩と葛藤は、もともと愛を至上のテーマとする宝塚にふさわしい作品であったのかも知れない。しかし、それは成功したあとの納得である。舞姫上演を聞いたときには、その結末も含め主人公の内面をどう舞台に載せるのか興味深かった。
さて舞台の幕が降りた時、感動のあまり私は席を立つことができない。しばらくして我に返って現実に戻りつつ、
「みわっち、やったね。みとさん。まっつも、みつるも、ちゃーもすごいぞ。(※1)みんな一つにまとまって。これは甲子園の優勝チームだ。監督は植田景子だ」と心の中で叫びつつ動けない。こんな新鮮な感動を覚えた作品は久方ぶりと言って良い。
外の一つ一つの短い文は主人公の内面をえぐりながら、風景を叙述するが如く客観性を備えている。こと
さら時代背景を記述しようとしない。しかしそれは紛れもなく、欧米列強に肩を並べんとする明治の日本である。
演出家植田景子は、太田豊太郎を今一度、100年後のこの時代から見つめ直し、その歴史、日本民族の中におき、もう一度現代の舞台に再生した。
この熱意と求心力が、出演者を動かしたのだろうか。愛音羽麗主演となれば、本人にとっては大挑戦である。
彼女はそれを乗り切った。エリスを演じた野々すみ花、彼女の最近の演技には定評がある。官長黒沢の白鳥かすが、こんな役をこんな風にできたのか。ただ驚愕。そして、新境地に挑む日本人として奮闘する画家芳次郎の華形ひかる。
登場人物すべてが持ち場をこなし、無駄のないせりふで舞台が進行していく。植田演出は、豊太郎を大日本帝国憲法の起草者とし祖国愛をより一層高い段階で演出する。個人の尊重と対立する古い日本の倫理観に支えられた家族愛、その極致である母の自害。芳次郎にスープを拒否し「おかゆ」を所望させ、望郷の念をより高次で演出することにより、豊太郎の葛藤をより美しくもり立てる。極めつけが最後の「襁褓」を「舞扇」に変えたこと。狂っても美しい。妖しいまでに美しい、これが宝塚の美の極致。すべて納得。
これは久々の会心作である。明治の文豪が生んだ作品を題材に、宝塚の愛をテーマに描く、その試みの大成功に、30年宝塚を観てきたファンの一人として大賛辞を送りたい。
舞台は出演者の単純総和ではない。観るものに感動を与えるもっとも大きな要素は、カンパニーを構成するすべての出演者、演出家がそのベクトルを一つにして舞台を仕上げていくその力である。そんなことに思い至った舞台、それが「舞姫」である。願わくはこのチームで上京(※2)することを切に切に望む。
すみれ・ひまわりの会会長
シゲニー・イートン
<注>
※1 宝塚の劇団員のことは生徒といいますが、生徒の皆さんには、芸名のほかにそれぞれ愛称があります。文中に出てくる愛称は以下のとおりです。
「みわっち」愛音羽麗(あいね・はれい)
「みとさん」梨花ますみ(りか・ますみ)花組副組長
「 まっつ 」 未涼亜希(みすず・あき)
「 みつる 」華形ひかる(はながた・ひかる)
※2 この作品は宝塚バウホールという宝塚大劇場に併設されている小劇場で公演された。バウホール公演に
はいろいろな企画があるが、主役は各組の2番手、3番手クラスが務めることが多く、トップスターへの登竜門。東京では日本青年館などで上演されることも多いが、中には東京公演の予定がない作品もあり、この「舞姫」がまさにそうである